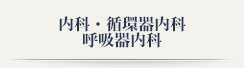内科の診察
内科疾患は頭から足の先まで種々の疾患があります。
当クリニックは内科疾患全般の診療や地域のホームドクター的な役割はもちろんのこと、最近増加傾向にあるメタボリック症候群を含めた生活習慣病の管理を積極的に行うことにより続発する循環器疾患の予防にも専念したいと考えています。

検診などで生活習慣病を御指摘された患者様は是非、一度ご相談ください。
循環器内科の診察
患者様は病院・診療所の看板や広告で循環器内科という言葉をよく目にすることと思います。
しかし、「循環器内科って?」具体的にはどんな病気を診療しているのでしょうか?
循環器内科とは、内科系の病気の中で特に心臓や血管に関する病気を専門に診療している科のことです。
どのような症状や病気の時に循環器内科を受診すればよいのかを具体的にまとめましたので参考にしてください。
- 胸や背中が痛くなったり、苦しくなる
- 息切れする・息苦しくなる
- 動悸がする・脈が速い・脈が遅い・脈がとぎれる(あるいは脈が飛ぶ)
- めまいがする・意識がなくなる
- 足がはれる・むくむ
- 歩くと足がだるくなる・痛くなる
- 健康診断や人間ドックで異常を指摘され方
具体的な疾患例
呼吸器内科の診察
呼吸器内科は、のど・気管・気管支・肺など、呼吸器に関する臓器の病気を専門的に扱う内科です。
「風邪だと思っていたが、咳が長引いている」など、咳や痰、息切れ、息苦しさなど呼吸症状が目立つ場合は、呼吸器内科を受診してみましょう。